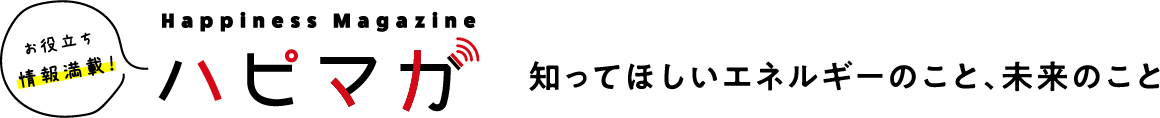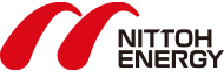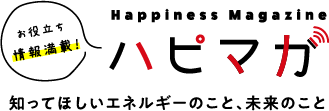【2025年5月最新版】リフォームに関する補助金制度 まとめ
 知っ得豆知識
知っ得豆知識

2025年4月現在、日本全国で利用可能なリフォーム関連の補助金・減税制度について、関東圏の事例も意識しつつ解説します。一般家庭が直接利用する制度と、リフォーム業者(施工業者)が申請窓口となる制度があります。以下では、各制度の目的や対象工事、申請要件、補助額、申請方法、運営主体、そして活用のポイント・注意点について詳しく説明します。
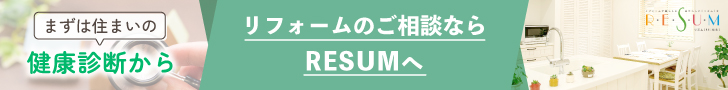


 最後に、複数の補助制度を横断して共通する利用上のポイントや注意事項をまとめます。リフォーム補助金は種類が多いため、上手に活用するための総合的なアドバイスです。
最後に、複数の補助制度を横断して共通する利用上のポイントや注意事項をまとめます。リフォーム補助金は種類が多いため、上手に活用するための総合的なアドバイスです。


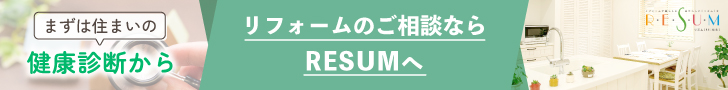

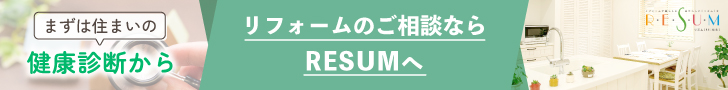

国が実施する主なリフォーム補助制度(2025年)

介護保険における住宅改修支給制度(バリアフリー改修)
概要と目的
高齢者や要介護者が安全に在宅生活を送れるように、住宅内のバリアフリー化を支援する制度です。介護保険の一部として位置づけられ、介護予防や生活環境の改善を図る目的があります。 各市区町村が窓口・事務を担当し、制度全体の所管は厚生労働省(介護保険制度)です。財源は公的介護保険から支出されます。対象住宅・工事
在宅の要支援・要介護認定者が居住する住宅における小規模なバリアフリー改修が対象です。具体的な工事内容は、- 段差の解消
- 手すりの設置
- 滑り防止床材への変更
- 扉の交換(引き戸等へ)
対象申請者
介護保険の要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている本人、もしくはその家族が申請者となります。要介護認定が前提条件となりますので、まず市区町村の介護認定を取得することが必要です。補助金の上限・補助率
上限20万円までの工事費用に対し、費用の7~9割を支給(自己負担1~3割)します。自己負担割合は所得に応じて変わり、低所得の場合は1割負担、高所得の場合は3割負担となります。例えば20万円の工事なら、自己負担2万円(1割負担の場合)で済む形です。なお、この上限額は同一要介護者につき一生涯で20万円までとなり、原則1回限りの利用です(転居した場合等は再度利用可能なケースもあり)。 申請方法・必要書類・受付: 工事の事前申請制です。居住地の市区町村役所(介護保険担当窓口)に対して、以下の手順で申請します。- ケアマネジャー等に相談し要介護者のケアプランに沿った改修が必要か判断
- 工事業者に見積を依頼し、工事内容の理由書(必要性を示すもの)、要介護認定書、住宅改修費支給申請書などを市区町村に提出(施工前の写真の提出を求められることもあり)
- 市区町村の承認を受領
- 完了後に領収書や施工後の写真とともに実績報告を提出
- 工事実施
- 市区町村から利用者(または代理受領の場合は業者)に補助金支給 ※注:事後申請は認められません。
注意点・活用のコツ
利用者の自己負担が少額で済むため非常に活用しやすい制度ですが、要介護認定を受けていることが前提です。また、20万円を超える部分は全額自己負担となるため、どの工事に優先的に補助を充てるか計画しましょう。ケアマネジャー等と相談し、「本当に必要な改修」に絞って使うのがコツです。工事着工前の申請が必須であること、領収書類の整備など手続きが煩雑なので、工事業者やケアマネに手続きサポートを依頼するとスムーズです。市区町村によっては独自に20万円を超える部分への助成を行う場合もあるので、地元自治体の高齢者住宅改修助成も併せて確認すると良いでしょう。子育てグリーン住宅支援事業(旧・子育てエコホーム支援事業)
概要と目的
2025年創設の新しい支援制度で、2050年カーボンニュートラルの実現と子育て支援を両立する目的があります。エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯などを重点に、省エネ性能の高い住宅の新築取得や既存住宅の省エネリフォームに対して補助金を交付する国の事業です。2024年までの「子育てエコホーム支援事業」を発展・拡充させたもので、国土交通省・経済産業省・環境省の三省連携で運営されます。対象住宅・工事
対象申請者
補助金の直接の交付先はリフォーム業者等ですが、事業を利用するエンドユーザーとしては、新築では建築主・購入者、リフォームでは工事発注者(住宅所有者)が対象です。子育て世帯・若者夫婦世帯(18歳未満の子どもがいる、または夫婦いずれか39歳以下)であれば新築取得補助が手厚くなります。ただし、実際の申請手続きは登録事業者(住宅施工業者等)が代行する仕組みです。補助額の上限・補助率
新築住宅の場合
性能ランクと世帯属性により1戸あたり40~160万円の定額補助です。具体例として、- 段差の解消
- 手すりの設置
- 滑り防止床材への変更
- 扉の交換(引き戸等へ)
- 開口部の断熱改修(窓・ドアの断熱性向上)
- 外壁・屋根・床など躯体の断熱改修
- エコ住宅設備(高効率給湯器等)
申請方法・必要書類・受付期間
この事業は「住宅省エネ2025キャンペーン」のポータルサイトで一元管理されており、申請は基本的にリフォーム業者やハウスメーカー等の登録事業者が代理で行います。一般の施主(消費者)は直接申請できない仕組みです。 施主は事前に補助対象工事に対応する「グリーン住宅支援事業者」(住宅省エネ支援事業者登録をしている施工業者)に工事を依頼します。2024年11月22日以降に着手した工事が対象で、業者が工事完了後または途中で交付申請をオンラインで行います。必要書類は工事請負契約書、工事の内容明細、写真(施工前後)、補助対象製品の証明書などです。 2025年(令和7年)2月から受付開始し、予算上限に達するまで随時受付の見込みです。公式には2025年12月末頃まで交付申請受付が想定されています。ただし早期に予算消化が進む可能性があるため、早めの申請が推奨されます.事務局による交付決定後、補助金は一旦登録事業者に支払われ、最終的に工事代金の値引きやキャッシュバックという形で消費者に還元されます。注意点・活用のコツ
リフォームは子育て世帯でなくてもOKですが、新築補助は一般世帯より子育て・若者夫婦世帯の方が補助額が高いです。該当するか必ず確認しましょう。 なお本事業は、後述の「先進的窓リノベ(環境省)」や「給湯省エネ事業(経産省)」とワンストップ併用可能です。つまり窓改修や高効率給湯器設置は、それぞれ環境省・経産省の補助を組み合わせ、一度の申請で両方の補助を受けることもできます(その場合、窓改修は環境省事業扱い、給湯器は経産省事業扱いとして処理)。複数制度の活用で補助額を最大化できるメリットがあります。 自分で申請できないため、登録事業者である施工業者に依頼する必要があります。事前に公式サイトで登録事業者を検索したり、リフォーム会社に確認するとよいでしょう。予算消化が早いと受付終了が前倒しされる可能性があります。2024年の前身事業では年内に終了した例もありました。早めの予約申請制度もあるため、工事契約後すぐに業者に申請してもらうのがポイントです。性能証明書類や写真等、申請書類が多岐にわたるので、信頼できる業者と十分に連携しましょう。特にエコ住宅設備や断熱材の型番・性能証明、工事前後写真の撮影は取りこぼしがないよう注意が必要になります。 土砂災害特別警戒区域内の住宅など一部対象外要件があります。建築地や住宅規模など要件を事前に公式資料でチェックしましょう。市区町村によっては独自に20万円を超える部分への助成を行う場合もあるので、地元自治体の高齢者住宅改修助成も併せて確認すると良いでしょう。先進的窓リノベ2025事業(高性能断熱開口部の改修支援)
概要と目的
環境省が実施する、既存住宅の窓・ドア等開口部を高性能な断熱仕様に改修するリフォームに対する補助制度です。エネルギーロスの大きい開口部を断熱化することで、住宅の省エネ化・CO2削減、光熱費負担軽減、快適性向上を早期に実現するとともに、高性能窓市場の拡大による価格低減や関連産業の成長を目指す事業です。令和6年度補正予算1350億円が充てられた大型事業で、2023年の「先進的窓リノベ2023/2024」の後継として2025年も実施されます.対象住宅・工事
戸建住宅・集合住宅を問わず、既存住宅の窓およびガラス、ドアの断熱改修工事が対象です。具体的な工事内容は,- ガラス交換: 既存サッシを活かし単板ガラスを複層ガラスに交換など
- 内窓設置: 既存窓の内側に新たな樹脂製内窓を追加設置
- 外窓交換: 既存窓サッシを丸ごと取り替える(カバー工法=壁を壊さず枠カバー設置、またははつり工法=一部外壁を壊して新設)
- ドア交換: 玄関ドア等を断熱性能の高い製品に交換(カバー工法・はつり工法)
対象申請者
住宅所有者等の工事発注者が実質的な補助対象者ですが、申請手続きは施工業者(窓リノベ事業者)が行います。消費者(施主)は自ら申請できないため、対象工事を依頼する際は「あらかじめ本事業に登録した窓リノベ事業者」(リフォーム業者)であることが必要です。なお、過去に先進的窓リノベ事業の補助を受けた同じ窓部位は対象外です(一度補助した窓の再改修は不可)。補助金の上限額・補助率
補助額は工事で設置する製品毎に定額で決まっており、その合計が支給額となります。窓の大きさ(面積区分)と性能(ガラスの断熱性能等)に応じて1箇所あたり数千円~数万円程度の補助額が設定されています。例えば内窓設置で小窓なら1万円、大窓なら2万円、といったイメージです(※具体額は製品性能区分による表があります。 1戸当たり最大200万円が補助上限です。小規模な部分断熱から、大規模な全窓交換まで幅広くカバーしますが、上限以上は自己負担になります。また、申請する工事の補助額合計が5万円以上でないと申請できません。つまり小規模工事で補助総額が5万円未満だと対象外です。窓2~3箇所以上の改修が目安となります。補助率としては定額補助なので一律ではありませんが、高性能窓への改修費用のおおむね1/2程度が補助で賄われるイメージです(製品種類によります)。申請方法・必要書類・受付期間
こちらも登録施工業者による代理申請です。流れは子育てグリーン住宅支援のリフォームに近く、窓改修に詳しいリフォーム会社(サッシ業者等)が登録事業者となっています。工事契約前に、その業者が「先進的窓リノベ2025事業」に参加登録済みか確認しましょう。 2024年11月22日以降着工の工事が対象で、原則工事完了後に交付申請を行います(事前の予算予約申請も可能な場合あり)。申請はWEB上で業者が行い、必要書類として契約書、施工前後写真、補助対象製品の証明、窓のサイズ・性能区分に関する書類等を提出します。2025年3月頃から申請受付開始(公式サイト開設は2024年末~2025年初頭)し、予算枠に達するまで受付予定です。2025年12月まで随時申請可能ですが、これも先着順で予算消化となるため、できるだけ早期に申請するのが望ましいです。審査後に補助金額が確定し、事務局から施工業者に支払われます。業者はその額を工事費値引きなどで施主に還元します。注意点・活用のコツ
窓リフォームの補助金も直申請は不可なので、信頼できる登録業者に依頼することが鍵です。必ず事前登録された高性能窓製品を選ぶ必要があります。製品型番が補助対象リストに載っているか、業者に確認しましょう。対象外品だと補助金が受けられないため注意です。 あくまで窓・ドア断熱改修限定の補助なので、内装工事等他のリフォーム費用には使えません。ただし前述のグリーン住宅支援とのワンストップ申請では、窓改修は本事業で補助を受けつつ、例えば同時に行うエコ給湯器設置は給湯省エネ事業で補助、残りの断熱工事は子育てグリーン住宅支援から補助、という併用が可能です。包括的にリフォームするなら併せ技で活用しましょう. 先進的窓リノベは窓専門の補助であり、補助上限額200万円と高額なため、大規模な全窓断熱リフォームに向きます。一方、子育てグリーン住宅支援事業のリフォーム枠(上限60万円)にも窓改修は含まれますが、補助額が少ないため、一戸あたり数十万円以上規模の窓工事をするなら本制度を使うのが断然有利です。補助金交付までタイムラグがあるため、一旦工事費全額を施主が立替えるか、業者が立替えるかを契約時に決めます。多くの場合、施主は補助見込額を差し引いた金額を支払う(業者が後で補助金受領)方式となっていますが、事前に確認しましょう.給湯省エネ2025事業(高効率給湯設備導入支援)
概要と目的
経済産業省 資源エネルギー庁が進める、省エネ給湯器の普及促進事業です。家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯を高効率化することで、2030年度のエネルギー需給目標の達成に寄与することを目的とします。2024年実施の「給湯省エネ2024事業(エコキュート補助)」の継続拡充版で、ヒートポンプ式(エコキュート等)やハイブリッド給湯器、エネファームなどの導入費用を補助します.対象住宅・設備
戸建住宅・マンション等を問わず、以下の高効率給湯設備を新規設置または交換設置する工事(新築・リフォーム・既存住宅購入時も含む)が対象です.- 電気ヒートポンプ給湯器(いわゆるエコキュート)
- ハイブリッド給湯器(電気ヒートポンプ+ガス瞬間式の併用型)
- 家庭用燃料電池(エネファーム)
- (加えて、高効率ガス給湯器(エコジョーズ)も性能要件を満たせば含まれる場合あり)
対象申請者
新築の場合は住宅の建築主または購入者、リフォームの場合は工事発注者(住宅所有者)、中古住宅購入時に給湯器交換する場合はその購入者が対象です。ただし、これも申請実務は登録事業者(施工業者や販売事業者)が行います。補助を受けるには、工事契約や機器購入をする相手が「給湯省エネ事業者」として登録されている必要があります。個人のDIY設置などは対象外です.補助金の上限・補助額
補助金額は以下3つの合計です.- 基本額: 導入する給湯器の種類ごとに定額補助。例えば、エコキュートは6万円/台、ハイブリッド給湯器は8万円/台、エネファームは16万円/台など機器種別で定められています。一戸につき台数上限(戸建2台、集合住宅1台等)があります。
- 性能加算額: 機器の中でも高性能モデルに対して追加補助。例えばエコキュートで高効率タイプなら+4~7万円/台、ハイブリッド給湯器でも+5~7万円/台の加算が設定されています。性能区分A・B・Cなど条件を満たす場合に適用されます.
- 撤去加算額: 既存住宅リフォームで古い電気温水器や蓄熱暖房機を撤去する場合、電気温水器撤去で4万円/台、蓄熱暖房機撤去で8万円/台の補助。各1~2台までが上限です。*エコキュートの撤去は対象外
申請方法・必要書類・期間
子育てグリーン住宅支援等と同様、工事を請け負う施工業者等がオンライン申請します。機器販売店や設備業者も登録できます。消費者は自分で申請せず、工事契約時に「補助金活用したい」旨を業者に伝えるとよいでしょう。新築の場合は建築会社、リフォームの場合は施工業者、既存住宅購入の場合は販売不動産会社がそれぞれ申請を担当する想定です。購入後リフォームの場合など少し特殊な区分もあるため、事務局FAQを参照してください。 機器の型式証明、工事前後の写真(既存給湯器と新設給湯器)、追加部品の写真(ヒートポンプユニットや貯湯ユニットなど)、撤去機器の写真など写真提出が非常に重要です。加えて契約書や領収書、製品の保証書写しなどを求められます. 事務局HPは2025年2月末に開設され、登録製品リストが公表後、2025年4月頃から交付申請開始の見込みです。2025年12月末まで(予定)受付ですが、予算580億円に達すると早期終了します。特に人気のエコキュート補助は前年早期に上限到達したため、早めに申し込みましょう。審査後、補助金は施工業者に支払われます。その分を請求額から控除する形で施主に渡るか、事前に値引きで反映されます。注意点・活用のコツ
本事業を利用するには、補助を受ける住宅のCO2削減相当量を国のJ-クレジット制度に提供する意思表示が必要です。これは手続き上、申請画面で同意するだけですが、補助対象者にとって実質的な不利益はありません(逆に言えば、CO2削減分のカーボンクレジットを国に譲る代わりに補助を受ける仕組みです)。 DIYの機器購入/設置、建売購入で既に高効率機器付き住宅を買う場合(既設機器の再設置でない限り対象外)、賃貸オーナーが空室住戸に設置(個別要件あり)などは対象にならないことがあります。必ず公式要件を業者と確認しましょう。エコキュートでも全てが対象ではなく、一定の省エネ性能基準を満たす製品のみです。事務局が型番リストを公表しますので、対応製品を選定してください。ガス給湯器単体(エコジョーズ)の場合、ハイブリッドではなく効率108%以上等の要件がないと対象外です。 蓄熱暖房機・電気温水器撤去への加算措置は予算32億円に達し次第終了とされています。エコキュート普及に伴う古い深夜電気温水器の撤去促進策ですが、予算枠が限られているため、該当する場合は早めに申請した方が良いでしょう. 子育てグリーン住宅支援事業のリフォームでエコキュート等に補助を受ける場合、本事業の補助は併用できません(重複不可)。つまり、エコキュートはどちらか一方の補助になります。補助額の大きい給湯省エネ2025事業を使う方が一般には有利です。なお、電気温水器撤去加算は子育てグリーン住宅支援と併用できないので注意が必要です。既存給湯器がない新築注文住宅でも、設置前のスペース写真が求められるなど、写真撮影のルールが厳格です。施工業者と協力して間違いなく撮影しておく必要があります。子育て支援型共同住宅推進事業(マンション・賃貸住宅の共用部改修・新築)
概要と目的
国土交通省の所管で、分譲マンションや賃貸アパートといった共同住宅における、子どもの安全・安心の確保と子育て家庭同士の交流促進につながる取り組みを支援する事業です。【令和3年度補正】で創設され2022年から実施されています。具体的には、共同住宅の共用部等において事故防止や防犯対策、およびキッズルーム等の共用施設整備などを行う場合に、費用の一部を補助します。あわせて宅配ボックス設置も子育て支援の一環(留守中の荷物受取利便性)として支援対象です.対象住宅・事業
賃貸住宅の新築(建設型): 保育園的な共用部を備えたり、安全設備を充実させた賃貸マンションの新築プロジェクト. 賃貸住宅の改修(改修型): 既存の賃貸アパート・マンションで共用部に安全設備やキッズスペースを増設・改修. 分譲マンションの改修: 分譲マンション(管理組合が申請主体)でエントランス等共用部分の安全対策工事や共用施設設置. 宅配ボックス設置のみ: 一定の子育て世帯割合を満たす既存共同住宅に宅配ボックスを導入する取り組み.- 段差の解消
- 手すりの設置
- 滑り防止床材への変更
- 扉の交換(引き戸等へ)
- 転落防止手すり(ベランダや階段)、窓の補助錠
- 防犯性の高い窓ガラス・玄関ドア、オートロック強化
- 共同住宅共用廊下や階段の滑り止め、照明の改善、人感センサーライト
- キッチンのチャイルドロック設備
- コンセントのシャッター式カバー、指はさみ防止ドアクローザー
- 火傷防止のサーモスタット水栓
- 集会室をキッズルーム兼用に改装、遊具の設置
- 屋外に砂場や小さな遊び場(プレイロット)を新設
- マンションの余剰スペースを改修して親子カフェスペースにする
- 扉の交換(引き戸等へ)
対象申請者
賃貸住宅の場合は事業主(デベロッパー、不動産オーナー)が申請者となります。分譲マンションの場合は管理組合が主体となり申請します(理事長名で申請、総会決議等が必要)。なお、申請には専門事務局への事前相談・事前審査を経る必要があり、コンサル会社等の協力を得て計画書を作成するケースもあります。補助率・補助上限
新築は対象経費の1/10、改修は1/3となっています。つまり、新築では10%、改修では33.3%の補助ということです。子どもの安全設備設置については100万円/戸が上限。例えば賃貸マンション10戸分を改修する場合、最大で100万×10戸=1000万円が上限(ただし補助率1/3適用なので実際はそのうちの1/3が補助金)となります。新築なら1/10なので上限100万でも実補助10万円/戸です。 居住者交流施設については1事業あたり500万円が上限。キッズルーム整備等は規模によらず500万円まで補助対象で、それを新築1/10・改修1/3します。改修なら最大で実質166.7万円補助になります。 宅配ボックスのみの場合は特殊で、1棟につき50万円固定補助(条件を満たせば一律で50万)という運用になっています。これは子育て世帯割合×経費×1/3の額を最大50万までとして算出するためですが、上限50万円/棟と覚えておけばよいでしょう.申請方法・必要書類・受付期間
まず事務局(子育て支援型共同住宅サポートセンター)への事前相談が必須です。計画内容が補助趣旨に合致するか、要件を満たすかを審査してもらいます。事前相談期間は年度ごとに設定されており、2025年度(令和7年度)は2025年4月1日~2025年9月30日(新築)および~2026年1月30日(改修)でした。 事前相談をクリアすると正式に交付申請できます。受付期間は2025年4月1日~2026年2月27日でした。申請書には事業計画書、図面、見積書、子育て世帯割合の証明(住民票一覧等)、マンションなら総会議事録などを添付します。募集要領に沿って提出し、予算枠内であれば交付決定されます。 交付決定通知後に工事着手、完了後は実績報告書を提出し、確定した補助金額が交付されます。なお子育て世帯の入居率3割以上など条件があるため、マンションなら住民構成の確認、賃貸なら入居募集要件として「子育て世帯限定期間」を設ける(新築賃貸では最初の3ヶ月は子育て世帯のみ応募可とする、など)運用も必要です。注意点・活用のコツ
この補助事業は公募制ですが、応募数が予算を下回る場合もあるため、しっかり要件を満たす計画なら採択されやすいです。マンションの共用部改修を予定しているなら、子育て支援の観点を組み込んで申請することで、管理組合にとってもコスト削減になります。賃貸オーナーにとっても、補助を受けて魅力的な子育て対応設備を整えれば物件価値向上・入居促進につながります。 原則、子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)が全体の30%以上居住する共同住宅でなければなりません。既存マンションでその割合が少ない場合、補助対象外になります。賃貸では新築時に一定割合子育て世帯を入居させる計画が必要です。個々の住戸内の設備も一部含まれますが(例:シャッター付コンセント等)、基本は共用スペースの改修がメインです。各戸内のキッチンや風呂等の改装は対象外です。管理組合で取り組みやすいエレベーターの防犯カメラや手すり設置などにフォーカスすると良いでしょう。 分譲マンションの場合、補助を受けるには総会決議で工事実施と補助申請の承認が必要です。区分所有者の理解を得るために、補助金が出るメリットや子育て世帯への支援意義を丁寧に説明することが大事です。補助金があることで管理組合の負担金(修繕積立金の取り崩し等)を抑えられる点をアピールしましょう。防犯カメラ設置や耐震改修など別の補助メニュー(自治体補助等)があれば、併用も検討します。ただし国の他の補助との重複は基本不可なので一事業で包括的にやるのがよいです。 宅配ボックスは比較的要件が緩く、子育て世帯割合3割以上の共同住宅なら、宅配ボックス設置費の1/3(上限50万)がもらえます。マンションの利便性向上として人気の設備なので、該当する場合はぜひ活用しましょう。 改修型では5戸以上の住戸に転落防止手すり等を設置することが求められるなど、ハードルがあります。要件の細かい読み込みと計画づくりが成功の鍵です。事前相談で不明点をしっかり確認することが大切です。補助金活用のポイントと手続き・注意点
 最後に、複数の補助制度を横断して共通する利用上のポイントや注意事項をまとめます。リフォーム補助金は種類が多いため、上手に活用するための総合的なアドバイスです。
最後に、複数の補助制度を横断して共通する利用上のポイントや注意事項をまとめます。リフォーム補助金は種類が多いため、上手に活用するための総合的なアドバイスです。
情報収集と制度確認を徹底する
リフォーム計画に入る前に、最新の補助金情報を集めましょう。制度は毎年改定・新設されるため、国交省や経産省の公式発表、キャンペーンサイト、新着ニュースを確認することが大切です。今回紹介した制度も2025年時点のもので、予算状況によっては内容変更や期間延長があります。特に国の補助金は年度単位で募集され、年度途中で終わることもあるので、「使えるはずと思っていたら締切後だった」という事態を防ぐためにも、計画段階からアンテナを張っておく必要があります。また、自治体独自の補助(耐震補助やアスベスト除去補助など)も多数あります。住宅リフォーム推進協議会の検索サイトや市区町村HPで地元の助成も調べて、国の補助と組み合わせて使えるか検討しましょう。登録業者・施工業者選びが鍵
多くの補助金は登録事業者制度を採っています。つまり、「補助金を使いたい」と思ったら、その制度に登録済みの施工業者に依頼することが条件です。したがって、リフォーム会社選びの段階で、「◯◯補助金に対応していますか?」と確認しましょう。例えば、住宅省エネ2025キャンペーン系の補助は共通の登録制度なので、大手リフォーム会社や工務店の多くは登録しています。一方、個人事業の小さな工務店など未登録の場合もあるので注意です。登録は無料かつ簡単なので、頼みたい業者が未登録なら登録を促すのも一つの手です。逆に、補助金制度に明るい業者は手続きにも慣れており、必要書類の段取りや注意点も理解しています。そうした業者に任せると、施主として負担が軽減され、漏れなく補助を受けられるでしょう。補助金予算枠と申請タイミング
補助金は基本「早い者勝ち(先着順)」が多いです。国の大型予算でも、人気の制度は年度途中で受付終了することが珍しくありません。そのため、 計画が決まったらすぐに申請準備…工事契約が済んだら、着工前でも予約申請できる制度(グリーン住宅支援など)は早めに仮申請しておく。 施工時期を考慮…例えば冬場は窓補助のニーズが高まる等、混雑期を避ける。 事務局の予算公表をチェック…公式サイトで「予算執行率◯%」など随時発表される場合があります。それを見て間に合いそうか判断する。 また、年度末は駆け込み申請が殺到するので、事務局の審査が滞りやすいです。年明け~春に余裕を持って申請するのがベターです。一方、年度途中に補正予算で新規制度が始まるケースもあります(今回の子育てグリーン住宅支援事業のように)。その場合、情報解禁から申請開始まで期間が短いことが多いため、こまめにニュースを確認しましょう。なお、補助金には交付申請期限と完了報告期限が明確に定められています。「申請したのに工事が遅れて期限までに完了しなかった」ということがないよう、工程管理も大切です。必要書類の準備と管理
補助金申請・減税申告には、多くの書類や証明が必要になります。 契約関連: 工事請負契約書、工事見積書、領収書(または請求書)。 性能証明: 製品カタログや性能証明書、認定通知書(長期優良住宅認定など)。 写真: 施工前後の写真はどの補助でも極めて重要です。箇所ごとに撮影し、日付や内容が分かる整理をします。ピンぼけや撮り忘れがあると不交付になることも。 証明書: 増改築等工事証明書、耐震改修証明書、断熱改修証明書などは建築士等に依頼して発行してもらいます。これは減税申告にも必須なので原本を大切に保管。 世帯要件書類: 子育て世帯等要件がある場合は住民票や戸籍などで年齢・子供の有無を証明します。 その他: 補助金によっては、銀行口座情報、工事個所を示す図面、製品シリアルナンバーの写真など細かな指示があります。 提出書類は事業者任せにせず、自身でも控えを確保しておきましょう。特に領収書・証明書類は確定申告でも使いますし、後年税務調査で確認されることもあります。減税制度では**「補助金を差し引いた額」で50万円超か判断**するものがあります。補助金を受けると、その分工事費から除いた額を基準に要件を満たす必要があるので、補助金交付決定通知書なども保管し、税務申告時に控除額計算へ反映します。補助金と減税の併用・トータルメリットを考える
補助金を受けると、その工事費用については減税制度の控除対象額から差し引かなければならない場合があります(国税庁の定め)。例えば100万円の省エネ工事で20万円補助を貰ったら、減税工事費は80万円として計算します。ただし耐震改修だけは補助金を差し引かなくても良い特例があります。いずれにせよ、補助金と減税を組み合わせて最大限メリットを享受することが重要です。ケースバイケースですが、 大規模リフォームでは長期優良住宅化リフォーム補助+住宅ローン減税で二重にメリット。 省エネ&耐震改修では補助金(例えばグリーン住宅支援60万)+投資型減税25万+固定資産税減額1/3~2/3を併用。 バリアフリーは補助金(介護保険20万上限)と固定資産税1/3減税を。 窓リフォームは補助金(先進的窓リノベ)と省エネ投資減税を(一部除外あり)。 といった具合に、総額でいくら得するかを試算しましょう。リフォーム費用に対し、公的支援で30~50%相当戻ってくるケースも珍しくありません。なお、補助金と補助金の併用については、原則同一内容の工事で2重取り不可です(例えば窓改修を国交省と環境省で二重に貰うことはできない)。しかし別メニューなら併用可(窓は窓リノベ、給湯器は給湯省エネ、手すりは介護保険、のように)なので、リフォーム工事をパーツに分けて最適な制度を当てはめるのがコツです。これらの調整は専門知識が必要なため、施工業者やFP(ファイナンシャルプランナー)などに相談してみてください。おわりに
リフォーム補助金は適切に活用すれば数十万~百万円単位のメリットがあります。一方で手続きや要件も多いので、本記事を参考にしながら計画的に準備し、信頼できる専門家の助けを借りて進めることをおすすめします。住宅のリフォームは家族の安全・快適性を向上させ、さらに公的支援で負担軽減も図れる絶好の機会です。ぜひ制度を賢く使いこなし、理想の住まいづくりに役立ててください。あわせて読みたい
※テスト環境では読み込みが動作しないため、記事のタイトルとリンクを貼ります。
▼バナーをCLICK! 「太陽光・蓄電池・V2Hの導入は今が一番おトク!」


▼バナーをCLICK! 「リフォームのご相談ならRESUMへ」
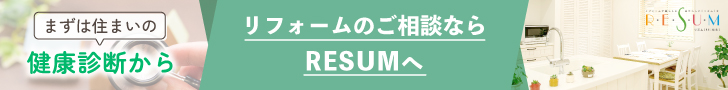

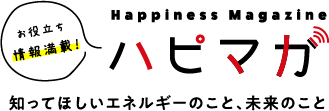
 環境
環境
 エンタメ
エンタメ
 キャンペーン
キャンペーン
 日東エネルギーグループ
日東エネルギーグループ